ピッタリの屋根修理の匠は見つかりましたか?
「どの屋根修理の匠を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や屋根に対してのお悩み・ご要望などからピッタリの職人をご案内します。
仲介手数料や紹介料はもちろん無料、しつこい営業等も一切いたしませんので安心してご利用ください。

屋根修理は、費用が高くなりやすい工事のひとつです。
「雨漏りが気になるけれど、どれくらい費用がかかるのか不安」「できるだけ負担を減らしたい」という方も多いのではないでしょうか。
実は、京都市や京都府では屋根修理や耐震改修に使える補助金制度が用意されており、条件を満たせば数十万円単位の支援を受けられる可能性があります。
この記事では、現在京都市で利用できる主な補助制度をわかりやすく整理し、申請の流れや注意点、そして補助金に対応できる信頼性の高い業者を選ぶポイントまで詳しく解説します。
なお、すべての情報は京都市・京都府の公的サイトをもとに構成しております。
屋根修理を検討している方が、「安心して・ムダなく・賢く修理できる」ように、ぜひ最後までお読みください。
Contents
京都市の「すまいの耐震・防火補助制度(通称:まちの匠・ぷらす)」は、住宅の耐震化・防火性能の向上を目的とした支援制度です。
木造住宅や京町家を対象に、耐震診断から改修工事まで一貫して補助が受けられます。
特に、屋根の軽量化や屋根構面(屋根下地)の補強といった工事も対象となるため、屋根修理を検討している方にとって非常に活用しやすい制度です。
令和7年度(2025年度)は支援拡充の最終年度とされており、補助上限額は最大300万円に引き上げられています。
(※ただし、屋根改修の場合は「簡易改修屋根型」に当てはまるため、木造住宅で最大20万円、京町家で最大30万円が補助金額となります)
また、従来は一部地域のみ対象だった「防火改修」も、京都市全域へ対象が拡大されました。
この制度は年度ごとに申請枠が限られるため、早めの相談・申請が安心です。
京都市が公開している案内資料では、以下のようなメニューが示されています。
・屋根の軽量化(瓦から金属屋根などへの変更)
・屋根構面の強化(下地補強・野地板の改修など)
・防火性能の向上(不燃材の使用、屋根裏・外壁の防火施工)
工事内容によって補助限度額が異なり、耐震診断を伴うかどうかでも対象金額が変動します。
案内冊子は年度ごとに更新されるため、申請前には最新版(京都市公式サイト)を必ず確認しましょう。
屋根修理の際に「断熱性能を高めたい」と考える方には、京都市が運営する「脱炭素ポータルサイト」掲載の断熱改修支援もチェックしておきたいところです。
この制度では、住宅の断熱性能を高めるための改修工事を支援しており、屋根断熱・天井断熱も条件を満たせば補助対象になります。
対象となる建材には、断熱性能や施工面積などの要件が定められています。
たとえば、以下のような工事が該当します。
・屋根裏や天井への断熱材追加
・断熱塗料や高遮熱塗料を用いた屋根塗装
・既存屋根の断熱リフォームを伴う葺き替え
ただし、この制度は年度ごとに受付期間・対象条件・補助金額が変更される点に注意が必要です。
申請を検討する際は、京都市の脱炭素ポータルサイトで最新情報を確認してください。
屋根修理や耐震リフォームを検討している方は、京都市の制度だけでなく、京都府が実施する「木造住宅耐震改修等事業費補助」にも注目してみましょう。
この制度は、耐震診断を受けた木造住宅の耐震性能(評点)を一定水準まで引き上げる改修工事を対象に、改修費用の一部を支援するものです。
補助率は改修費用の5分の4(80%)で、上限額は原則100万円または120万円とされています(※京都府住宅建築課・木造住宅耐震改修等事業費補助 公式情報より)。
さらに、令和6年度・令和7年度は制度の拡充期間にあたり、改修後の耐震評点が1.0以上になる場合など、条件を満たす住宅では上限額が引き上げられる特例措置が設けられています。
ただし、この補助制度は市町村が事業主体として運用しているため、申請や要件の詳細は自治体ごとに異なります。
京都市にお住まいの方は、京都市 建築指導課または都市計画局が窓口となるため、まずは市の窓口で確認することが確実です。
なお、京都市が行う「すまいの耐震・防火補助制度(まちの匠・ぷらす)」と、京都府の制度を併用できるケースもあります。
屋根の軽量化や構造補強など、両方の補助対象に該当する改修内容であれば、自己負担額を大幅に減らせる可能性があります。
制度には築年数や構造の条件もあります。たとえば、京都市の制度では、
木造住宅:昭和56年5月31日以前に着工した建物
京町家:昭和25年11月22日以前に建築された建物
が主な対象となります。
対象の可否は、建築年や構造形式によって異なるため、早めの確認がおすすめです。
屋根の軽量化や耐震補強を計画する際は、府と市の両方の制度を比較・相談しながら進めることで、より賢く費用を抑えることができるでしょう。
京都市が実施する「すまいの耐震・防火補助制度(まちの匠・ぷらす)」は、屋根の軽量化や防水改修など、耐震性・防火性を高める工事に活用できます。
ここでは、「屋根修理の匠」に登録している京都市内の優良業者による実際の施工事例をご紹介します。
いずれも制度を活用し、補助金を受けながら安全で長持ちする屋根へと改修されています。
築約40年の瓦屋根で、台風被害による再発雨漏りが課題となっていた住宅です。
京都市の補助制度「まちの匠・ぷらす」を活用し、補助金20万円を受けて屋根の全面葺き替えを実施。
重い瓦を撤去し、軽量で高耐久なSGL鋼板製「スーパーガルテクト」を採用しました。
あわせて雪止めと換気棟を設置し、耐震性・防水性・断熱性をバランスよく強化。
仕上げは「シェイドブラック」で、外観も美しく刷新されました。
★『山口板金』の業者紹介ページはこちら!
築80年を超える木造住宅で、老朽化した瓦屋根の軽量化を目的に葺き替えを実施。
昭和25年以前の建物が対象となるため、京都市の補助金30万円を受けて工事が行われました。
施工では、劣化した瓦と下地を撤去し、構造補強を行ったうえで、ガルバリウム鋼板による「立平葺き」工法を採用。
継ぎ目が少なく、排水性に優れた構造のため、雨漏りに強く耐久性も抜群です。
★『大村ルーフ』の業者紹介ページはこちら!
雨漏りはなかったものの、今後の耐震性を考えて屋根を軽量化したいとのご相談から、京都市の屋根軽量化補助金を利用してスーパーガルテクトへの葺き替えを実施しました。
瓦を撤去後、新しい下地とルーフィングを施工し、軽量かつ高耐久の金属屋根に刷新。
下屋根には立平葺きカバー工法を採用し、排水性と防水性を強化しました。
同時に外壁塗装も実施し、足場費用を抑えながら外観全体の美観も向上。
耐震・断熱・防水のすべてを高めたリフォーム事例です。
★『大村ルーフ』の業者紹介ページはこちら!

屋根修理や耐震リフォームを検討する際、京都市と京都府の両方に補助制度が存在します。
どちらを利用すべきか迷う方も多いですが、実はそれぞれの制度は目的が異なるため、適した使い分けを意識することが大切です。
屋根の軽量化や防火・断熱といった「住まいの快適性や安全性を幅広く向上させたい」場合は、京都市の制度が適しています。
一方で、「建物全体の耐震性能を数値的に強化したい」「耐震診断で低い評点が出た」という場合には、京都府の制度のほうが合致するケースが多いです。
どちらを選ぶかは、「工事の目的が部分的(屋根中心)か、構造的(家全体)か」で判断すると分かりやすいでしょう。
京都市と京都府の制度は、対象工事や申請主体が異なるため、内容によっては併用も可能です。
ただし、手続き上の重複や書類提出のタイミングには注意が必要です。
とくに次の3点を押さえておきましょう。
同じ工事費を重複して申請することはできません。
どの部分をどちらの制度で補助申請するか、見積もり段階で整理しておくことが重要です。
京都府の制度も市町村が事業主体となって運用されているため、京都市内の住宅であっても窓口は京都市の建築指導課になります。
補助金は予算上限に達すると早期に受付が締め切られることがあります。
毎年度、4月〜6月頃に公募が始まる傾向があるため、早めに動くのが安全です。
補助制度を正しく活用するには、制度に詳しい施工業者に相談することが近道です。
業者が制度内容を理解していれば、申請に必要な書類(工事計画書・見積内訳書・施工証明など)を正確に整えられます。
また、「まちの匠・ぷらす」では代理受領制度があり、施工業者が申請者に代わって補助金を受け取れる仕組みも整っています。
この制度を活用することで、自己負担額が明確になり、手続きの手間も軽減できます。
京都市の「まちの匠・ぷらす」は令和7年度で支援拡充の最終年度とされており、制度終了が予定されています。
一方、京都府の補助制度も令和6・7年度の特別拡充が設けられているため、今がまさに申請の好機といえます。
どちらの制度も、受付状況や条件が年度ごとに変わるため、「屋根修理を考えてから調べる」ではなく、早い段階で制度情報を確認することが大切です。
屋根の軽量化・防火・断熱 → 京都市の「まちの匠・ぷらす」
建物全体の耐震性能強化 → 京都府の「木造住宅耐震改修等事業費補助」
条件が重なる場合は併用も検討可能
制度を上手に使い分けることで、屋根修理費を大幅に削減できます。
特に京都市では、相談から申請、施工までを支援する仕組みも整っています。
「屋根修理の匠」では、こうした補助金制度を熟知した地域の専門業者をご紹介しています。
費用面の不安を減らし、安心して工事を進めるために、ぜひ一度ご相談ください。
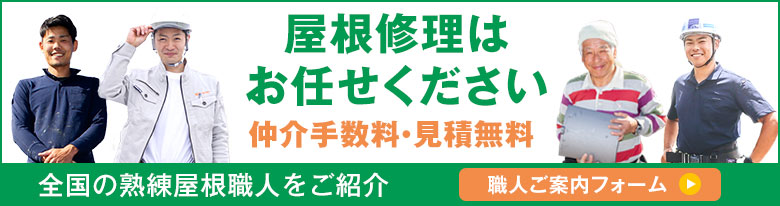

補助金制度を活用する際、「すべての屋根工事が対象になる」わけではありません。
実際には、申請条件を正しく理解しないまま工事を進めてしまい、不採択になってしまうケースも少なくないのです。
ここでは、特に見落とされやすいポイントを整理します。
屋根の塗り替えや小規模な補修は、「性能の向上」が伴わない場合、補助の対象外となることがあります。
たとえば、美観を整えるだけの再塗装や、一部の瓦の差し替えなどは原状回復的な工事とみなされ、補助金が適用されません。
京都市の「すまいの耐震・防火補助制度(まちの匠・ぷらす)」では、「屋根の軽量化」や「構面の強化」といった建物の耐震性能を高める改修が対象として明記されています。
つまり、単なる修繕ではなく、住宅性能を向上させることが求められるのです。
補助制度では、工事を始めてからの申請は一切認められません。
「とりあえず工事を進めて、後から補助を申請しよう」と考えると、補助対象から外れてしまいます。
申請には見積書、耐震診断の結果、設計内容など、事前に用意すべき書類が多くあります。
そのため、着工前に必ず市や府の許可を得ることが必要です。
このルールは京都市・京都府だけでなく、府内全域で共通の原則となっています。
補助金は、性能向上に必要な部分に対して支給されます。
そのため、以下のような費用は対象外となる場合があります。
・足場の設置費用(全体の安全確保目的の場合)
・雨樋や破風板など付帯部の補修
・屋根以外の外構・庭・設備に関する工事
また、設計費や調査費、住宅ローン返済なども補助対象外です。
見積もりを取る際には、「補助対象費用がどこに含まれているか」を明確にしておくと安心です。
京都市・京都府の補助制度は、年度ごとに要件や金額が変わることがあります。
実際に、京都市の「まちの匠・ぷらす」では、令和7年度をもって制度の拡充最終年とする旨が発表されています。
また、京都府の「木造住宅耐震改修等事業費補助」でも、令和6・7年度は補助上限を一部引き上げるなどの拡充措置が取られています。
要綱や手引きには、補助対象となる工事内容、提出書類、補助金上限などが細かく定められています。年度が変わると条件も変わるため、申請前に必ず最新版の公式資料を確認しましょう。
業者が補助金対応を代行できる場合もありますが、最終的な申請責任者は施主本人です。
「業者が申請してくれるから安心」と思い込むと、書類不備や制度誤解によって申請が通らないこともあります。
補助金の上限や対象条件を自分でも把握しておけば、業者との打ち合わせや見積もり確認がスムーズに進みます。
結果的に、不正請求やトラブルの防止にもつながるのです。
補助制度は年度途中に受付を終了することもあります。
そのため、申請を検討する際は、最新情報を必ず以下の公的サイトでご確認ください。
京都市「すまいの耐震・防火補助制度(まちの匠・ぷらす)」
京都府「木造住宅耐震改修等事業費補助」
京都市脱炭素ポータル「既存住宅の断熱改修支援」

補助金を活用した屋根修理は、申請から受領までに複数の手続きを経て進みます。
各ステップを正しく理解しておくことで、スムーズに補助金を受け取ることができます。
以下は、京都市「すまいの耐震・防火補助制度(まちの匠・ぷらす)」を中心に、京都府の補助制度にも共通する一般的な流れをまとめたものです。
(※制度や年度によって詳細が異なる場合があります)
まずは、京都市の担当窓口(都市計画局 建築指導部 住宅政策課)または、登録建築士・協定施工業者に相談します。
「対象となる建物か」「耐震診断が必要か」などを確認し、現地調査を依頼します。
京都市の「まちの匠・ぷらす」では、登録事業者が制度要件に沿って耐震診断・工事計画を立てる仕組みが整っています。
この段階での相談内容が、申請の可否を左右する重要なステップです。
現地調査の結果をもとに、施工内容と概算費用を算出します。
屋根の軽量化、構面の強化、外壁との取り合いなどを踏まえて、改修メニューを整理します。
補助対象となるのは、耐震性・防火性の向上に資する工事費・設計費・報告費用などです。
見積時点で補助対象外の費用(外構工事・単なる塗装など)が混ざらないよう確認が必要です。
交付申請には、主に次のような書類を提出します。
・申請書・事業計画書
・工事見積書
・改修内容の図面や説明書
・建物登記簿謄本、所有者確認書類
・耐震診断結果(必要な場合)
京都市・京都府ともに、写真や図面などの添付が求められる場合があります。
交付決定前に着工した工事は補助対象外となるため、必ず決定通知を待ってから契約・施工に進みましょう。
書類審査を経て、補助金交付が認められると「交付決定通知書」が届きます。
この通知を受け取って初めて、正式な契約・着工が可能となります。
京都市公式要項にも、「交付決定前の着手は補助対象外」と明記されています。
このタイミングまでは見積・相談段階に留めておきましょう。
交付決定通知を確認したら、施工業者と正式に契約を結びます。
契約書には、工事範囲・工期・金額・保証条件を明記し、補助対象費用が反映されているかを確認します。
工事が始まったら、施工状況の写真記録をしっかり残しておきましょう。
京都市の制度では、工事中の写真を完了報告時に提出するよう定められています。
制度や工事内容によっては、進捗段階で中間的な確認や追加資料の提出を求められる場合があります。
耐震補強や構造改修などでは、特に下地や補強箇所の記録写真が重視されます。
業者任せにせず、施主自身も内容を把握しておくと、後の報告がスムーズになります。
工事が完了したら、現地での確認と報告書類の提出を行います。
提出書類には次のようなものがあります。
・完了報告書
・施工写真(施工前・施工中・施工後)
・領収書・請求書の写し
・必要に応じて工事変更届
完了報告の期限は、制度ごとに明確に定められています。
京都市「まちの匠・ぷらす」では、令和8年3月1日までの提出が指定されています(2025年度現在)。
検査・報告書類の審査を経て、補助金が支払われます。
受け取り方式は以下の2つです。
代理受領方式:補助金が施工業者へ直接支払われ、施主は自己負担分のみ支払う方式
施主受領方式:施主がいったん全額を支払い、完了後に補助金が振り込まれる方式
京都市の「まちの匠・ぷらす」では、代理受領制度が運用されています。
どちらの方式かは契約時に確認しておくと安心です。
はい。京都市の「すまいの耐震・防火補助制度(まちの匠・ぷらす)」では、屋根の軽量化を目的とした簡易改修も補助対象に含まれています。
耐震診断を伴う本格改修だけでなく、瓦屋根から軽量金属屋根への葺き替えなど、住宅の安全性を高める工事も対象となります。
ただし、築年数や構造、工事内容によっては補助対象外になる場合もあります。
必ず事前に京都市 都市計画局 建築指導部の担当課、または制度に詳しい施工業者へ相談しましょう。
(参照:京都市 都市計画局 建築指導部「すまいの耐震・防火補助制度(令和7年度)」)
現時点では、屋根塗装のみの工事は補助対象外です。
「まちの匠・ぷらす」は、建物の耐震性・防火性の向上を目的とした制度であり、塗装による美観の回復や防水メンテナンスのみでは対象になりません。
ただし、塗装と同時に屋根下地の補強や軽量化工事を行う場合には補助対象となるケースがあります。
また、省エネ改修系の支援(例:屋根断熱や遮熱塗装)については、京都市の「脱炭素ポータル」に掲載される年度事業で対象となることもあります。
年度ごとに要件が変わるため、最新情報の確認が重要です。
京都市 脱炭素ポータル
できません。
京都市の制度では、交付決定前に着工した工事は原則として補助対象外です。
申請→審査→交付決定→着工、という流れを守る必要があります。
申請から決定までには通常1か月前後かかるため、余裕をもって準備することが大切です。
条件を満たせば、京都府の「木造住宅耐震改修等事業費補助」と併用できる場合もあります。
ただし、同じ工事内容について市と府の両方から重複して補助を受けることは不可です。
京都市内にお住まいの場合は、市の制度が優先されるため、京都市の窓口(住宅政策課)で確認を行いましょう。
可能です。
ただし、申請には耐震診断書、工事見積書、施工計画書、完了報告書など専門的な書類が必要です。
多くの方は、補助金申請の経験を持つ屋根業者にサポートを依頼しています。
「屋根修理の匠」に登録している施工店の中には、申請書類作成や報告写真の整理などをサポートできる職人もいます。
補助金は工事完了後に報告書を提出し、審査を経て後払い(精算払い)で支払われます。
支払いまでの期間は、完了報告からおおよそ1〜2か月が目安です。
一部の工事では、施工業者が補助金を代理で受領し、施主の立て替え負担を軽減する方式に対応している場合もあります。
契約前に支払い方法を確認しましょう。
申請から交付決定まではおおよそ1〜2か月、工事完了後の交付まではさらに1〜2か月程度が一般的です。
ただし、年度末(1〜3月)は申請が集中するため、審査が遅れる傾向があります。
早めの申請をおすすめします。
京都市内にお住まいの方は、まず京都市 都市計画局 建築指導部 住宅政策課(電話:075-222-3613)に相談してください。
制度要綱や申請書式、提出先が公式サイトで公開されています。
また、「屋根修理の匠」に登録する地域業者では、現地調査と同時に補助金の適用可否チェックを行っています。
制度を理解した職人に依頼することで、無駄のない工事計画が立てられます。
交付決定前の着工は対象外となるほか、補助対象にならない費用(外構工事・設備費・塗装単体など)がある点に注意してください。
また、申請には写真記録や完了報告書などの証拠資料が必要です。
これらをきちんと整理してくれる施工業者を選ぶことで、審査がスムーズになります。
京都市では、耐震性や防火性能の向上を目的に「まちの匠・ぷらす(すまいの耐震・防火補助制度)」を実施しています。
屋根の軽量化や葺き替えなど、構造を改善する工事であれば補助対象となるケースが多く、最大300万円までの支援が受けられます。
また、京都府の「木造住宅耐震改修等事業費補助」との併用も可能で、条件次第ではより負担を減らすこともできます。
一方で、屋根塗装だけのメンテナンスや、交付決定前の着工は補助の対象外です。
「補助の対象になると思っていたのに採択されなかった」というケースも少なくないため、申請手順と要件の確認がとても大切です。
制度の仕組みや記録書類の整備には専門的な知識が必要なため、補助金の実績がある業者へ相談するのが安心でしょう。
「屋根修理の匠」では、京都市の補助金制度を活用した屋根リフォームに対応できる地域の専門業者を紹介しています。
現地調査のうえで制度適用の可否を確認し、申請から完了報告まで一貫してサポートします。
屋根の軽量化・耐震化を検討している方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
「どの屋根修理の匠を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や屋根に対してのお悩み・ご要望などからピッタリの職人をご案内します。
仲介手数料や紹介料はもちろん無料、しつこい営業等も一切いたしませんので安心してご利用ください。
LINEでかんたん
問い合わせ&職人案内