ピッタリの屋根修理の匠は見つかりましたか?
「どの屋根修理の匠を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や屋根に対してのお悩み・ご要望などからピッタリの職人をご案内します。
仲介手数料や紹介料はもちろん無料、しつこい営業等も一切いたしませんので安心してご利用ください。
住宅が築20年を迎えると、外壁や屋根といった外装部分には経年劣化が目立ち始めます。特に屋根は、普段目にする機会が少ないため劣化に気づきにくく、気づいたときには雨漏りや下地の腐食といった深刻なトラブルにつながっているケースも珍しくありません。
本記事では、築20年の屋根で起こりやすい劣化症状や、点検の目安、修繕方法や費用相場までを徹底解説します。後半では、信頼できる業者選びのポイントや、助成金制度についても触れますので、屋根リフォームや点検を検討している方はぜひ参考にしてください。
Contents

屋根は住宅を守る“盾”として、雨風・紫外線・気温変化・雪など、あらゆる自然環境の影響を受け続けています。そのため築20年を迎えると、屋根材そのものだけでなく、防水シートや下地、構造部分にも劣化が進んでいる可能性が高まります。見た目では大きな問題がないように見えても、内部では雨水の侵入や腐食が進行しているケースも少なくありません。
屋根材には種類ごとに耐用年数があり、築20年はちょうど分岐点といえる時期に当たります。
20〜30年程度。メンテナンスを行えば35年ほど持つケースもありますが、製造時期や製品によっては15年程度で不具合が出ることもあります。
25〜30年が一般的な耐久性ですが、最新の製品では30〜40年の寿命が期待できます。
瓦自体は30年以上〜100年近く持つ場合もありますが、漆喰や下地は20年程度で劣化が始まりやすく、メンテナンスが欠かせません。
このように築20年という時期は、屋根全体の寿命や耐用年数と重なりやすいため、放置すると不具合が一気に顕在化する可能性があります。
築20年を迎えた屋根は以下の理由から、点検・修繕を検討すべき重要なタイミングといえます。
色あせ、割れ、サビ、塗膜の剥離などが現れやすくなります。
防水紙(ルーフィング)や野地板は屋根材より早く劣化が進むため、外観に問題がなくても内部で雨水が侵入しているケースもあります。
台風や大雨などで、小さな劣化が大きな破損につながり、雨漏りや瓦・板金の飛散といった被害を引き起こす可能性が高まります。
築20年を迎える住宅では、外観が比較的きれいに見えても、屋根の内部や細部では劣化が進行しているケースが多くあります。特に屋根は常に雨風や紫外線、気温差にさらされるため、劣化の進み方が早く、放置すると雨漏りや構造体への影響に直結します。
ここでは屋根材ごとの劣化症状と、下地や防水層で起こりやすい問題を詳しく解説します。

スレート屋根は日本の住宅で広く採用されてきた屋根材で、軽量かつ施工性が高いことが魅力です。しかし耐久年数には限界があり、築20年を超える頃には以下のような症状が出始めます。
新築時に施された塗装は紫外線や雨により徐々に分解され、色あせやツヤの消失が起こります。手で触ると白い粉がつく「チョーキング現象」も典型的な劣化サインです。
長年の温度変化や乾燥によってスレートが反り、表面にひびが入ることがあります。小さなひびから雨水が浸入し、内部の防水シートや野地板に被害が及ぶことも少なくありません。
特に日当たりの悪い北側の屋根や湿気がこもりやすい場所では、コケやカビが繁殖しやすくなります。見た目が悪くなるだけでなく、保水性が高まるため劣化スピードを早め、防水性能を低下させます。

ガルバリウム鋼板やトタンといった金属屋根は、軽量で耐久性が高いとされますが、築20年を超えると次のような症状が顕著になります。
表面を保護している塗膜が紫外線や風雨で劣化し、金属部分がむき出しになると赤サビや白サビが発生します。特に海岸近くの住宅では塩害によってサビが急速に進み、穴あきや腐食に発展する危険性があります。
強風や地震による揺れで棟板金が浮いたり、固定している釘が抜けたりすることがあります。板金部分は屋根の接合部を守る重要な部位であり、ここからの浸水は雨漏りの直接原因になります。
劣化が進むと屋根材の密着性が低下し、雨音が大きく響くようになります。防音性や断熱性が下がることで、室内環境に影響が出るケースも見られます。

瓦屋根は非常に耐久性が高く、30年以上持つケースも珍しくありません。しかし瓦自体が丈夫でも、漆喰や下地といった周辺部材は築20年で劣化が目立ち始めます。
棟部分や瓦の固定に使われている漆喰は、風雨や乾燥で劣化しやすく、剥がれやひびが発生します。これを放置すると瓦がずれたり落下する危険があり、雨漏りリスクも増大します。
長年の地震や風の影響で瓦が少しずつずれ、隙間が生じることがあります。部分的な割れも見られ、そこから雨水が浸入するケースが多いです。
瓦屋根は重厚感が魅力ですが、その分住宅の構造に大きな負担をかけます。築年数が経つにつれ耐震性への不安が増し、補強工事が必要となる場合もあります。

屋根材だけでなく、屋根内部の下地や防水層も築20年で深刻な劣化が進むことが多いです。
雨水が浸入すると、野地板が湿気を含んで腐食します。屋根がたわむ、歩くと沈むといった症状が出れば、野地板交換や葺き替え工事が必要になります。
防水シート(ルーフィング)は屋根材の下で二次防水の役割を果たしますが、20年前後で寿命を迎えることが多いです。劣化すると防水性能が低下し、雨漏りが室内にまで及びます。
屋根裏で結露が発生すると断熱材が濡れ、性能が低下するだけでなく、カビや木材腐食の原因になります。特に通気性が悪い屋根構造では注意が必要です。

屋根の劣化は一見すると小さなヒビや色あせ、わずかな浮きなどに見えることもあります。
しかし、そのまま放置してしまうと想像以上に深刻なトラブルへと発展する可能性があります。特に築20年を超えた住宅では、屋根材そのものの寿命や下地、防水シートの劣化が重なり、一気に被害が表面化しやすいのです。
ここでは、劣化を放置した結果として実際に起こり得る代表的なトラブルを見ていきましょう。
最も気づきやすい症状は、天井や壁に現れる雨染みでしょう。はじめは小さなシミのように見えても、時間とともに広がり、壁紙が剥がれたり変色したりします。見た目の問題だけでなく、じめじめとした湿気はカビの発生源となり、室内の空気環境を悪化させることがあります。
特にお子様やご高齢の方がいらっしゃるご家庭では、アレルギーなどの健康問題につながる可能性もあるため注意が必要です。
屋根から雨水が浸入すると、屋根裏の木材(野地板や垂木など)が湿気を含み、腐食が進みます。湿った木材は残念ながらシロアリの格好の住みかとなり、知らないうちに屋根からはじまった被害が柱や梁にまで広がることもあります。
このような状態になると、単なる屋根修理だけでなく、住宅全体の構造補強や防蟻工事が必要になり、工事の規模も費用も大きくなってしまいます。
初期段階であれば、屋根材の部分交換や塗装といった比較的小規模な対応で、数十万円程度で修繕できることが多いです。
しかし、劣化を放置してしまうと、下地や防水層まで傷みが進行し、葺き替えや重ね葺き(カバー工法)といった大規模な工事が避けられなくなります。このような工事では100万円から200万円以上かかることも珍しくなく、ご家庭の家計に大きな負担となります。
早めの点検と対応が「修繕費用を最小限に抑える一番の秘訣」といえるでしょう。
将来住宅を売却する際には、屋根の状態は必ず専門家によってチェックされます。雨漏りの跡や天井のシミが見つかると、それだけで査定額が大幅に下がり、数百万円も減額されることがあります。
また、購入をお考えの方にとって「雨漏りのある家」は不安要素となり、売れにくくなったり値引き交渉の対象になったりします。大切な資産価値を守るためにも、屋根の劣化はできるだけ早く対処することをお勧めします。
雨漏り修理で固定資産を守る!雨漏りが建物の価値を損う理由と対策を徹底解説!

築20年というのは、住宅にとってひとつの大きな節目といえます。屋根材は常に紫外線や雨風にさらされており、経年による劣化は避けられません。たとえばスレート屋根なら約20〜25年、金属屋根でも25〜30年が耐用年数の目安とされており、築20年は寿命の限界が迫るタイミングと重なります。
この時点で点検を怠ると、屋根材表面の劣化だけでなく、防水シートや野地板の腐食といった内部の不具合が一気に表面化し、雨漏りや構造材の損傷といった重大トラブルへ直結します。特に地震や台風といった自然災害に見舞われた際には、すでに傷んだ屋根が被害を拡大させる要因となり、修繕費用が数百万円単位に膨らむことも珍しくありません。築20年を迎えたら「まだ大丈夫」と油断せず、必ず専門業者による点検を受けることが重要です。
屋根の点検は一度きりで済むものではなく、定期的に繰り返すことで住宅の寿命を大きく延ばせます。一般的に推奨されるサイクルは次の通りです。
この時期から屋根表面に色あせや小さなひび割れが出やすくなります。早期発見によって小規模補修で対応できるケースが多いのが特徴です。
屋根材の種類や立地条件によって劣化の進行は異なりますが、5年ごとの点検を習慣化することで、劣化のサインを見逃さずに済みます。
見た目に大きな損傷がなくても、強風で棟板金が浮いていたり、大雨でルーフィングが損傷していたりするケースがあります。災害後は一度点検を受けることで、早期に被害を最小限に抑えられます。
屋根の点検はプロに任せるのが基本ですが、日常生活の中でも住まいの異変を察知できるサインがあります。屋根に直接上る必要はなく、地上や室内から確認できるポイントだけでも定期的にチェックしておきましょう。
たとえば、室内では天井や壁に現れる雨染み、クロスの剥がれ、カビの発生などが代表的な兆候です。外部では、雨樋の詰まりや屋根材の破片が落ちている場合、屋根材の一部が割れているか剥離している可能性があります。さらに、屋根表面の色あせや塗膜の剥がれ、苔や藻の繁殖なども劣化のサインといえます。これらの症状は一見すると軽微に思えますが、その裏で防水層や下地材に深刻なダメージが進行しているケースが多く、早急な点検と対応が必要です。
プロによる点検では、ドローンを使った空撮、直接屋根に上がっての点検、屋根裏からの確認など多角的な調査が行われます。
屋根修理専門業者は専門性が高く正確な診断が可能。一方、工務店は建物全体を見てもらえるメリットがあるものの、屋根に特化した診断力はやや弱い傾向があります。信頼できる業者を見極めるには、写真や動画での説明、明確な見積書、アフターサポートの有無を確認しましょう。
築20年を迎えた屋根は、劣化の程度や損傷の部位によって、適切な修繕方法が大きく変わります。表面的な不具合で済む場合もあれば、下地や防水シートにまで傷みが及んでいることもあり、その判断には専門的な点検が不可欠です。主な選択肢としては「部分補修」「カバー工法」「葺き替え」の3つが挙げられます。
屋根全体ではなく、傷んでいる箇所だけを直す方法です。例えば、棟板金(屋根の頂上部分の金属)の交換、割れた瓦やスレートを新しいものに差し替える、塗装が剥げている部分だけ再塗装するなどが挙げられます。お財布に優しいのが大きな魅力ですが、根本的な解決策ではないので、いわば「応急処置」と考えるのがよいでしょう。
築20年の屋根では、見た目の修繕だけで十分な場合もありますが、見えない部分(防水シートや下地の木材)が傷んでいると、表面だけ直しても数年後にまた問題が出てくることが少なくありません。
屋根全体が古くなっているけれど、下地や防水シートはまだ健全な場合におすすめの工法です。既存の屋根はそのままにして、その上から新しい金属屋根などを被せます。工事期間が短く、古い屋根材を処分する費用も抑えられるのがメリットです。特にスレート屋根のリフォームでよく使われ、暑さ対策や防水性能を高めることで、家全体の住み心地も良くなります。
ただし、もともとの屋根が重い場合や下地が傷んでいる場合には向かないため、事前にプロによる点検で適しているかどうかの判断が必要です。
屋根の土台となる木材や防水シートまで劣化が進んでいる場合、部分補修やカバー工法では対応しきれません。そんなときに選ぶべきなのが「葺き替え」です。既存の屋根材をすべて撤去して、防水層から新しくやり直すので、これからの30年以上を見据えた安心できる屋根に生まれ変わります。
費用も工事期間も3つの中では一番かかりますが、耐震性・防水性・耐久性のすべてにおいて最も確かな方法といえます。特に築20年を超えて屋根全体に問題が見られる場合や、何度も雨漏りに悩まされている住宅には、この葺き替えをおすすめしています。
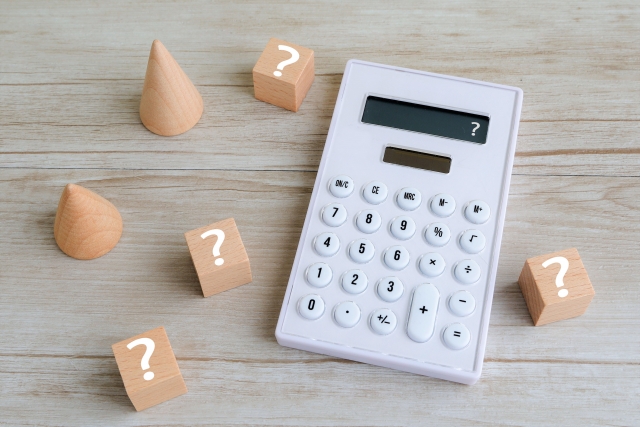
築20年を迎えた屋根の修繕費用は、工法の選び方や劣化の具合によって大きく変わってきます。ここでは一般的な相場をご紹介しますので、参考にしてみてください。
棟板金の交換や割れた瓦の差し替え、部分的な塗装などの小規模な修繕が該当します。比較的お手頃な価格で対応できますが、見えない部分の劣化まで解決できるわけではなく、数年後に再度修理が必要になることもあります。
今ある屋根材はそのままで、その上から新しい屋根材を重ねる方法です。工事期間が短く、古い屋根材の処分費用も節約できるため、コストパフォーマンスに優れた工法として多くの方に選ばれています。特にスレート屋根のリフォームでよく用いられます。
既存の屋根を全て撤去して、防水シートや下地から新しく作り直す方法です。費用は高めになりますが、これから30年以上安心して暮らせる耐久性が得られるため、長い目で見るとメリットの大きい選択肢です。耐震性や防水性も大幅に向上します。
屋根工事では安全確保のために必ず足場を設置します。別々の時期に工事すると、そのたびに足場費用がかかってしまうので、屋根と外壁を同時にリフォームするなど工事をまとめることで、かなりの費用節約につながります。
このように、同じ築20年の屋根でも、劣化の進み具合や選ぶ工法によって費用に大きな差が出ることをご理解いただくことが大切です。複数の業者から見積もりを取り、工事内容が適切かどうかをしっかり確認されることをお勧めします。
屋根リフォームは決して安い投資ではありませんが、費用負担を軽減できる制度が複数用意されています。上手に活用することで、安心してリフォームを進めることができます。
台風や雪害、飛来物の落下など自然災害による被害であれば、火災保険が適用される場合があります。屋根材の破損や雨漏り修理費用が補償されるケースもあり、自己負担を大幅に軽減できる可能性があります。ただし経年劣化は対象外のため、申請時には専門業者による調査報告が必要です。
多くの自治体では、省エネや耐震性向上を目的としたリフォームに対して補助金を用意しています。屋根の遮熱塗装や軽量屋根材への葺き替えなどが対象となることもあり、数万円から数十万円の補助を受けられる可能性があります。各自治体で条件や受付期間が異なるため、事前確認が欠かせません。
リフォームローンを活用することで、まとまった支出を分割して計画的に返済できます。また、省エネ改修や耐震補強を伴うリフォームであれば、住宅ローン減税の対象となる場合もあります。ローン金利や返済条件を比較検討することで、無理のない資金計画を立てられます。
このような制度を組み合わせることで、大きな出費となる築20年の屋根リフォームも、経済的な負担を和らげながら実施することが可能です。
築20年は屋根の寿命に差し掛かる重要な時期です。劣化症状を見逃すと、雨漏りや構造腐食など大きなトラブルに発展し、修繕費用が跳ね上がる可能性があります。
定期的な点検と早めの対応こそが、住まいを守り、資産価値を維持する最善策です。
「屋根修理の匠」では、地域密着で信頼できる屋根のプロをご紹介しています。築20年の屋根点検やリフォームをお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
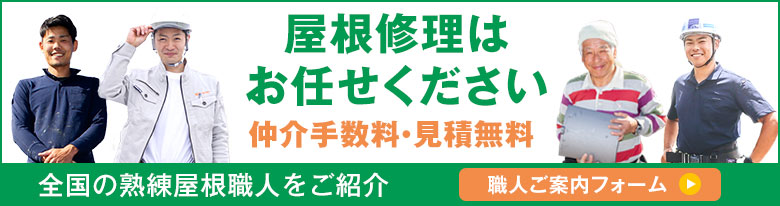
「どの屋根修理の匠を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や屋根に対してのお悩み・ご要望などからピッタリの職人をご案内します。
仲介手数料や紹介料はもちろん無料、しつこい営業等も一切いたしませんので安心してご利用ください。
LINEでかんたん
問い合わせ&職人案内