ピッタリの屋根修理の匠は見つかりましたか?
「どの屋根修理の匠を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や屋根に対してのお悩み・ご要望などからピッタリの職人をご案内します。
仲介手数料や紹介料はもちろん無料、しつこい営業等も一切いたしませんので安心してご利用ください。

「瓦屋根」は、今もなお多くの住宅で使われている屋根材のひとつで、採用・メンテナンスを検討している方も多いのではないでしょうか。しかし、瓦屋根にはあらゆる種類があり、それぞれの特徴やメンテナンス方法がいまいち分かりづらいですよね。
そこで今回は、瓦屋根の特徴やメリット、デメリットについて分かりやすく解説していきます。
「瓦屋根のメンテナンス方法を知りたい」「どんな瓦を選べば良いかわからない」といった方は、ぜひ参考にしてください。
Contents
瓦屋根は、種類によって特徴やメンテナンス方法が異なります。はじめに、瓦屋根の種類や特徴について理解しておきましょう。
瓦屋根の種類は、大きく分けて次の3つとなります。
・粘土瓦
・セメント瓦
・樹脂セメント瓦
それぞれの特徴をくわしく見ていきましょう。
粘土瓦とは素材である粘土を瓦の形にして、高温で焼き上げて作ったものを指し、さらに細かく「釉薬瓦」と「無釉薬瓦」に分類されます。
釉薬瓦とは、焼き上げる前に液体のしみ込みを防いだり、色やツヤを出したりする効果がある「釉薬」を塗布した瓦のことをいいます。釉薬瓦は「陶器瓦」ともよばれており、さまざまな色合いを出せるだけでなく、変色しづらいという特色があります。
一方、無釉薬瓦とは釉薬を使わない瓦を指し、「いぶし瓦」や「素焼き瓦」などはその一種です。いぶし瓦とは、焼き上げた後にいぶすことで、瓦の表面に炭素膜が生成し、渋い銀色に仕上がるのが特徴です。また、素焼き瓦とは使用した粘土の色が活かされるので、自然な色合いを堪能できるのが特徴といえます。
加えて、最近は「軽量防災瓦」を採用する住宅も増えています。軽量防災瓦とは、従来における粘土瓦の重量よりも軽量化された瓦のことで、建物への負担が少なく、耐震性の向上が期待できます。また、瓦のズレや浮きを防止するために、瓦同士の結束力を強化する工夫もされています。
セメント瓦とは、セメントを主成分としたものを型にいれて、形成し塗装した瓦のことです。セメント瓦は大量生産しやすく、以前までは多くの住宅で採用されていましたが、ガルバリウム鋼板といった低価格な金属屋根が展開された背景により、現在はあまり使われていません。
樹脂とセメントのハイブリッドによる「樹脂セメント瓦」は、現在普及率を高めています。なかでも、屋根製造会社のケイミューが「ルーガ」という商品を出したことは、住宅業界で大きな話題となりました。ルーガの成分は「樹脂混入繊維補強軽量セメント瓦」に分類され、セメントを主原料とした陶器瓦のような質感が特徴です。従来の陶器瓦やセメント瓦と比較して、ルーガは軽量でなおかつ強い耐久性があると評価されています。
日本には、産地の良質な土を使って作られた「日本3大瓦」といわれる粘土瓦があります。日本3大瓦は、それぞれの産地に適した特徴を持っているほか、高い技術力により今もなお多くの住宅で採用されている、長い歴史のある瓦です。
日本3大瓦は、次の3つとなります。
・三州瓦
・石州瓦
・淡路瓦
ひとつずつ特徴を探ってみましょう。

三州瓦は愛知県三河地方が産地で、最も生産量が多い瓦として知られています。三州瓦は1,100℃以上の高温で焼き上げられているため、耐久性や耐火性が高いほか、水分を吸収しないという特徴から、防水性や耐寒性も優れています。

石州瓦は島根県石見地方で生産されていて、赤褐色の赤瓦が特徴的です。どの瓦よりも高い1,200℃で焼き上げて生成されている石州瓦は、最も耐寒性に優れているといえるでしょう。また、塩害にも強いことから沿岸地方でも多く採用されています。

淡路瓦は兵庫県淡路島で作られていて、いぶし瓦の生産数が多いことでも有名です。淡路島では、いぶし瓦に適した「なめ土」という良質な土が採れることにより、いぶし瓦のシェア率1位を実現しています。淡路島周辺の大阪・京都・奈良の神社や寺院でも、屋根材にいぶし瓦が多く採用されているのが特徴です。
瓦屋根には種類の違いだけでなく、形状にも違いがあります。形状が異なると、部分的な交換ができないといったリスクもあるため、あらかじめ形状の違いを理解しておくことが大切です。
屋根瓦の形状は、次の4種類があげられます。
・J型
・F型
・S型
・M型
それぞれの違いを見てみましょう。
J型は「和型」ともよばれていて、緩やかなカーブを描いた瓦屋根の代表的な形です。一般住宅だけでなく寺院や神社にも使われていて、「JAPAN」の頭文字をとったという説もあります。
F型は「平板瓦」とよばれることもあり、平らな形状の瓦を指します。和風住宅のみならず洋風住宅にも採用されているほか、太陽光パネルを載せた住宅でも多く採用されています。Fには「Flat」の頭文字をとったという説や、フランス瓦を参考にしたのでFになったという説もあります。
S型は、緩いS字を描いている断面が特徴の洋風瓦を指します。「Spanish」の頭文字をとったことが由来といわれていて、洋風住宅に使われることが多い瓦です。
M型は、S型と比較して凹凸が深い瓦のことをいいます。S型と同様、洋風住宅に使われることが多く、軽量であることが大きな特徴です。

瓦屋根にはどのようなメリットがあるのでしょうか。瓦屋根の強度や価格、デザイン性などあらゆる観点から、種類ごとにメリットを紹介します。
粘土瓦のメリットは次の3つです。
・耐久性が高い
・遮熱性と断熱性が高い
・防音性に優れている
粘土瓦は高温で焼き上げて作られているため、耐久性が非常に強く、基本的には塗装が必要ありません。実際に、日本の寺院で1,400年以上使用されているという実績があるほどです。また、空気層が多いため遮熱性や断熱性、防音性にも優れているのが特徴です。
セメント瓦のメリットは、以下の3つとなります。
・デザイン性が高い
・耐火性に優れている
・コストを安く抑えられる
セメント瓦は形や色のバリエーションが豊富で、建物の雰囲気に合わせやすいといったメリットがあります。また外気温の変化に強く、耐火性に優れているので安心です。
一方、セメント瓦はセメントを主成分とした材料を流し込んで形成するだけなので、他の瓦と比べると製造にコストがかからず、大量生産することが可能です。よって、屋根材の価格やメンテナンス費用も抑えられることがメリットとしてあげられるでしょう。
樹脂セメント瓦のメリットは、次の3つです。
・軽量で耐久性が高い
・断熱性が高い
・割れにくい
樹脂セメント瓦は、従来の瓦屋根と比べて重量が半分ほど減り、建物への負担も軽減できるため、耐震性を強化することができます。また、屋根材と下地材の間の空気層が多いため、断熱性アップの効果もあります。さらに、樹脂セメント瓦には繊維材料が含まれていることにより、繊維が補強材として働き、割れにくい性質を実現しています。
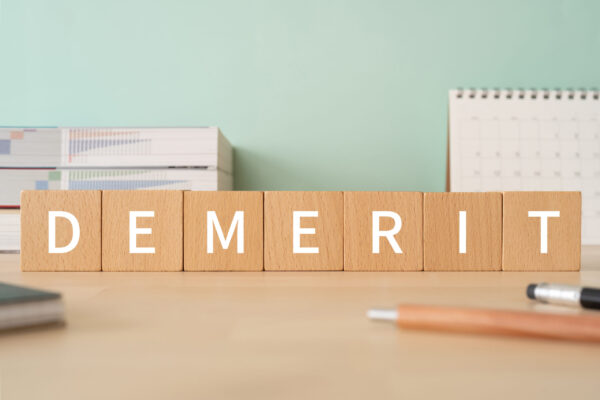
瓦屋根は、メリットが多く優れた屋根材ではあるものの、いくつかのデメリットもあります。ここからは瓦屋根のデメリットについて、種類ごとに理解しておきましょう。
粘土瓦のデメリットは、下記の2つです。
・価格が高い
・重量があり耐震性に欠ける
粘土瓦は強度が高く、長持ちしやすい屋根材ではあるものの、価格の高さがネックとなります。他の屋根材と比較しても価格が高いため、メンテナンス費用も費用が高くつくでしょう。また、瓦屋根には重量があり、建物の構造に大きな負担がかかってしまうため、耐震強度に影響を及ぼすリスクがあります。
セメント瓦のデメリットは、下の2つです。
・定期的な塗り替えが必要
・防水性に乏しい
セメント瓦は塗装仕上げの瓦です。また瓦自体に防水性はなく、定期的な塗装によるメンテナンスが不可欠です。塗り替えるメンテナンスを怠ると、瓦が傷んだりひびが入ったりして、雨漏りの要因になりかねません。セメント瓦は紫外線や経年による劣化が著しいため、一層の注意が必要です。
樹脂セメント瓦のデメリットは、次のとおりです。
・販売実績が少ない
・価格が高い
樹脂セメント瓦の代表格として展開されている「ルーガ」は、2007年に販売された比較的新しい商材なので、耐久年数の実績や評価の少なさがネックとしてあげられます。また、屋根材の価格が高いこともデメリット。ルーガは施工に専用の部材が必要であるほか、従来の瓦屋根よりも工期が長いため、材料費に加えてメンテナンス費用も高くつくでしょう。
以下のように、瓦屋根は種類ごとに耐用年数が異なります。
| 瓦の種類 | 耐用年数 |
| 粘土瓦(釉薬瓦) | 50年〜100年 |
| 粘土瓦(無釉薬瓦) | 30年〜50年 |
| セメント瓦 | 30年〜40年 |
| 樹脂セメント瓦(ルーガ) | 30年(目安) |
上記の耐用年数は、あくまでも適切なメンテナンスを施した場合の年数です。たとえば釉薬瓦の場合、屋根材自体のメンテナンスはほぼ不要ですが、20年を目安に下地材の交換が必須です。また、セメント瓦は10年〜15年ごとを目安に塗装によるメンテナンスが不可欠です。そのほかの屋根材に関しても、耐用年数が過ぎるタイミングで屋根材を交換するメンテナンスが必要になると心得ておきましょう。
瓦屋根のメンテナンス方法は、瓦屋根の種類や年数によって異なります。屋根材をきれいに維持するためにも、あらかじめ適切なメンテナンス方法をおさえておきましょう。
瓦屋根のメンテナンスは、主に以下の4つです。
・部分補修
・塗装
・葺き替え
・葺き直し
それぞれの特徴や適切な時期について見てみましょう。
瓦屋根は、屋根材の一部が割れたり破損したりするリスクがあります。たとえば、台風や強風による飛散物が屋根材にあたり、瓦屋根が破損したといったケースはよくある話です。もし、破損した瓦屋根を放置しておくと、その箇所から雨水が侵入し、家の雨漏りを引き起こすことも考えられます。
また、雪が積もったり台風が来たりすると、瓦屋根がズレてしまうことも。ズレが生じると隙間から雨水が侵入し、雨漏りを引き起こす要因となるためメンテナンスが必要になります。
部分補修では「屋根全体を交換する必要はない」といったときに、破損した部分を差し替えたり補修したりする施工が可能です。
セメント瓦は瓦自体に防水性がないため、10年〜15年ごとに定期的な塗装メンテナンスが必要です。なお、塗装は使用する塗料によって単価や耐用年数が異なります。
| 塗料 | 単価 | 耐用年数 |
| ウレタン | 1,500円〜2,500円/㎡ | 8〜10年 |
| シリコン | 1,800円〜3,500円/㎡ | 13〜15年 |
| フッ素 | 3,000円〜5,000円/㎡ | 15〜20年 |
また、塗料には遮熱機能がある塗料や、汚れを落ちやすくする塗料もあるので、必要な機能性を基準に選ぶのも良いでしょう。
ただし、粘土瓦の場合は塗装によるメンテナンスが必要ありません。
葺き替えとは既存の瓦屋根を剥がして、下地材の交換・補修を行ったうえで新しい屋根材に交換する工法のことです。
葺き替えの場合、瓦屋根をスレートやガルバリウム鋼板に交換することで、屋根の軽量化を図れるほか、メンテナンス費用をおさえられます。もちろん、新しい屋根材に瓦屋根を採用することもできます。
「この家に長く住む予定がある」「屋根材の傷みが著しい」という場合は、屋根の葺き替えを選択しましょう。
葺き直しとは既存の屋根材を剥がし、下地材の交換・補修を行ったうえで既存の屋根材を再利用する工法のことです。
葺き直しは既存の屋根材を再利用するため、処分にかかる費用や新しい屋根材の材料費がかからず、トータルコストをおさえられるというメリットがあります。近い将来引っ越す予定があり、同じ家に長く住むつもりがない場合や、下地材のメンテナンスのみしたい場合は、葺き直しでコストを抑えるのが得策です。
ただし、屋根材の傷み具合によっては「葺き直し」ではなく「葺き替え」せざるを得ないこともあります。たとえば、粘土瓦よりも耐用年数が短いセメント瓦は、瓦自体の傷みと下地材の傷みが同時に進み、近い将来で葺き替えが必要になるため、葺き直しには向いていません。
特に耐用年数が長い「粘土瓦」は、下地材の傷みのほうが早く進行するため、定期的な葺き直しが必要になるでしょう。
続いて、瓦屋根のメンテナンス費用について見てみましょう。
| メンテナンス方法 | 費用相場 |
| 部分補修 | 〜5万円(足場代を除く) |
| 塗装 | 50万円〜100万円 |
| 葺き替え | 150万円〜200万円 |
| 葺き直し | 120万円〜180万円 |
部分補修に関しては、補修箇所によって足場が必要になる可能性があります。足場代を追加すると30万円近くになるため、足場の必要可否を依頼する業者に相談してみましょう。
また、塗装は使う塗料によって金額が変動します。必要であれば、外壁塗装も同時に施工すると足場を活かすことが可能です。
一方、葺き替えは選ぶ屋根材によって価格が変動します。もし価格を重視するなら、スレート屋根やガルバリウム鋼板への葺き替えを検討してみてください。葺き替えや葺き直しも同様に、外壁塗装が必要な場合は、足場を組んだときに同時に施工してもらうのが良いでしょう。
なお、上記の金額は屋根の面積や劣化の状態によって変動するため要注意です。
【関連記事】
ここからは、瓦屋根をメンテナンスする際の注意点について解説します。あらかじめ注意点を理解しないと、不利益を被る危険性もあるためしっかりおさえておきましょう。
カバー工法とは、既存の屋根材の上に新しい屋根材を被せる工法のことです。カバー工法は既存の屋根材を撤去する費用がかからないため、トータルコストをおさえられるのがメリットといえます。
しかし、瓦屋根はカバー工法によるメンテナンスに向いていません。なぜなら、波打つような形状の瓦屋根に新しい屋根材を被せることは困難であるからです。また、重量のある瓦屋根に新しい屋根材を被せると、さらに重さが増し、建物の耐震性能が低下するリスクが高まります。
したがって、瓦屋根をメンテナンスする場合は、屋根材の耐用年数や劣化状況を加味して「葺き替え」か「葺き直し」を検討しましょう。
【関連記事】
「地元の業者から屋根のメンテナンスについて訪問営業された」という話を耳にしたことはありませんか?無料点検という名目で屋根にあがり、屋根修理を提案されるという事例はよくある話です。しかし、中には悪質な業者がいるため注意が必要です。
実際に、訪問営業を受けた方から「屋根に問題があるといわれたけど、信頼できないから屋根修理の匠で登録している業者に見てもらいたい」という依頼が後を絶ちません。
したがって、訪問営業に来た業者の提案を鵜呑みにせず、情報収集したうえで判断することが重要です。
【関連記事】
瓦屋根を修理する際、状況によっては火災保険を利用してメンテナンス費用を抑えることが可能です。火災保険は、当時の被害状況がわかる写真と申請書類を提出し、申請の承諾を得ることで利用可能となります。
もし、台風や自然災害によって屋根瓦が破損したり剥がれたりした場合は、火災保険を活用してうまくメンテナンス費用を抑えましょう。依頼する業者によっては、火災保険の利用に精通している修理業者もいるので、依頼先に相談してみるのもひとつです。
【関連記事】
今回は瓦屋根の特徴やメリット、デメリットについて解説しました。瓦屋根は今もなお日本の住宅で多く採用されていて、耐久性に優れた屋根材です。
ただし、瓦屋根は他の屋根材と比べて重く、耐震性が懸念されるほか、屋根材の価格が高いため、ガルバリウム鋼板やスレート屋根といった軽量の屋根材が注目されるようになっています。
瓦屋根は種類や劣化状況によってメンテナンス方法が異なるので、メンテナンスの際はプロへの相談が必須です。屋根修理の匠では、各都道府県の優良屋根修理業者を探すことができるので「業者や屋根材の選択に不安がある」「屋根のメンテナンス方法がわからない」という方はぜひ活用してみてください。
「どの屋根修理の匠を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や屋根に対してのお悩み・ご要望などからピッタリの職人をご案内します。
仲介手数料や紹介料はもちろん無料、しつこい営業等も一切いたしませんので安心してご利用ください。
LINEでかんたん
問い合わせ&職人案内